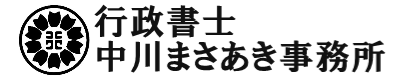�悭���鎿��
�s�����m�́u�g�߂ȊX�̖@���Ɓv�Ƃ��Ă��A��炵��r�W�l�X�̖@���葱���ɐ��ʂ������Ƃł��B���L���Ɩ���S���A�����������ɐE���𐋍s���邱�Ƃ��g���Ƃ��Ă��܂��B�@���Ɋւ��鑊�k�⏑�ލ쐬�Ȃǂ�ʂ��āA�����̐�������ɍv������������ʂ����܂��B��ʂ̕��X�ɂƂ��Ă��A���育�Ƃ̑��k��Ƃ��ċC�y�ɗ��p�ł��鑶�݂ł��B
�s�����m�Ɉ˗�����ƁA�ȉ��̗��_������܂��B
�ŐV�̖@���ɑΉ�: �@�����ɐ��ʂ��A���m�ȏ��ނ��쐬�B�X���[�Y�Ȏ葱��: �s����~�X��h���A�v���Ȑ\�����\
�B���S�y��: �ώG�Ȏ葱�����s���A�˗��҂͖{�ƂɏW���ł���
�B
��p�ʂł��L��: �ٌ�m��葊�k������߂ŁA�������k������
�s�����m�́A�O���l�̌ٗp����{���Ђ̎擾�Ɋւ��镡�G�ȏ��ލ쐬���T�|�[�g���܂��B
��Ȑ\���葱��:
�ݗ����i�F��ؖ�����t�\���i�V�K�����̂��߂̐\���j
�ݗ����i�擾�E�ύX�E�X�V���\���i�؍ݎ��i�̕ύX�E�����j
���i�O�������\���i�{���̍ݗ����i�O�̊������j
�i�Z���\���i���{�ł̒����؍��j
�A�����\�����쐬�i���{���Ў擾�̐\�����쐬�j
�s�����m�Ɉ˗����郁���b�g:
�\���掟�s�����m�Ɉ˗�����A�\���l�{�l�����ǂ֍s�����Ɏ葱���\�B
�A�����\���͖@���ǂ������ƂȂ邽�߁A�s�����m�����ޏ������T�|�[�g���܂��B
�����֍s����Ԃ⎞�Ԃ��Ȃ��邱�ƁA���Ƃ̏����ɐ�O�ł��邱�ƂȂǂ�����܂��B�s�����m�͒芼�̍쐬��芼�F�̑�s���\�ŁA��Ђɑ��������芼�������I�ɍ쐬�ł��܂�
�s�����m�́A�������ւ̐\�����ލ쐬���o��s�A�芼�̍쐬�E�F�ؑ�s�Ȃǂ��s�����Ƃ��\�ł��B �������A�o�L�\���Ɋւ�鏑�ނ̍쐬�E��o�͎i�@���m�̓Ɛ�Ɩ��̂��߁A�s�����m�͑Ή��ł��܂���B�K�X�A��g����i�@���m�搶�ւ����炩��˗����邱�Ƃœ�x��ԂɂȂ�Ȃ��悤�H�v���܂��B
������Ђ͍Œ�1���Őݗ��\�ł��B���傪����������C���邱�Ƃ��ł��A���̏ꍇ�A����1������\������߂܂��B �������A��������ݒu����ꍇ�́A�ȉ��̖������K�v�ł��B
������F3���ȏ�
��\������F1���ȏ�
�č����܂��͉�v�Q�^�i�ŗ��m�܂��͌��F��v�m�j�F1���ȏ�
�@�����1�~�ȏ�Őݗ��ł��܂��B�������A���Ƃ��c�ނɂ͎������K�v�ł���A���������邽�߂ɂǂꂭ�炢�̎������K�v���悭�������Ď��{���̊z�����߂�ׂ��ł��B�܂��A�c�����Ƃ��鎖�Ƃɍs���̋����K�v�ȏꍇ������A���̋��v���Ɏ��Y�̗v�����܂܂�邱�Ƃ����邽�ߒ��ӂ��K�v�ł��B
������Ђ�ݗ�����ɂ́A�ȉ��̗���Ői�߂܂��B
�芼�̍쐬: ��Ђ̖ړI�A�����A���ݒn�A���{���A�g�D�̐��Ȃǂ����肵�A���N�l���芼���쐬
�芼�̔F��: ���ؖ���Ō��ؐl�ɂ��F����
���{���̕���: ���O�Ɍ��߂����{�������Z�@�ւɕ�������
�ݗ��o�L�̐\��: �@���ǂ\���B�F�؍ς݂̒芼�⎑�{�������ؖ������o
�o�L����: ��1?2�T�Ԍ�ɓo�L���������A��Аݗ��������ɐ���
�o�L�\��������������Ђ̐ݗ����ƂȂ�܂��B
�����Ŏ葱�����s���ꍇ�A�ȉ��̔�p���K�v�ł��B
�芼�̈�: 4���~�i�d�q�芼�Ȃ�s�v�j
�芼�F�̌��ؐl�萔��: 5���~�i������Ђ͕s�v�j
�芼�̓��{��p: ��2,000?3,000�~�i������Ђ͕s�v�j
�o�^�Ƌ���: ���{���z��7/1000�i�Œ�15���~�A������Ђ͍Œ�6���~�j
���̑�: ��Ђ̑�\��A�o�L�����ؖ����A��ӏؖ����̎擾��p�Ȃ�
�s�����m�Ɉ˗�����ƁA��L��p�ɉ����Đ��Ƃ̕�V�i10���`15���~���x�j��������܂��B���\�����̎萔����K���m�F���ĉ������B
������ЈȊO�ɂ́A������ЁE������ЁE������Ђ�����܂��B
�������: �����ӔC�Ј��݂̂ō\���������
�������: �����ӔC�Ј��ƗL���ӔC�Ј������݂�����
�������: ������Ђ��葱�����ȗ��ŁA���ؐl�ɂ��芼�F���s�v
���݁A�V�����L����Ђ͐ݗ��ł��܂��A�ߋ��ɐݗ����ꂽ���̂͑������Ă��܂��B
�⌾���̎�ށi���M�؏��⌾�A�����؏��⌾�A�閧�؏��⌾�j�S�Ăɂ��č쐬�x�����\�ł��B�⌾�����@���Œ�߂�ꂽ�v�������A�⌾�҂̋C�������������`���悤�ɃT�|�[�g���܂��B�����؏��⌾�̍쐬�葱���T�|�[�g��A�⌾���s�҂̎w��Ɋւ��鏕�����s���܂��B
�����l�͈̔͂Ə��ʂ͖@���Œ�߂��Ă��܂��B
�z���: ��ɑ����l�i�������A�����̍Ȃ͑ΏۊO�j
��1����: �q�i�{�q�E�َ����܂܂��j
��2����: ���n�����i�e��c����ȂǁB�q�����Ȃ��ꍇ�ɑ����l�ƂȂ�j
��3����: �Z��o���i�q�E���n���������Ȃ��ꍇ�̂ݑ����l�j
��Y�������c���́A�����l���m�ň�Y�̕�������b�������A���̍��ӓ��e�𐳎��ɏ��ʉ��������̂ł��B
�K�v�ȏ��: �s���Y�̓o�L�葱������Z�@�ւł̑����葱���̍ۂɓY�t���ނƂ��Ē�o���K�v�ɂȂ�ꍇ������
�B�����h�~: ���O�ɍ쐬���Ă������ƂŁA��X�̃g���u����h���������ʂ����B
�s�����m�̃T�|�[�g: �����l�S���̍��ӂ�K�@�Ȍ`���ł܂Ƃ߁A�W�@�ււ̎葱����s���\�B
�����̕����Ƃ́A��Y����؈����p���Ȃ��ƌ��߂�@����̎葱���ł��B
����: �������Y�����p���Ȃ����Ƃ�@�I�Ɋm�肳����
�B�葱���̊���: �����Ƃ��āA�n�����ԁi3�����ȓ��j�ɉƒ�ٔ����\�q���K�v�B
�ӎv�m�F: �\���͖{�l�̈ӎv�Ɋ�Â��s���A�ٔ������K�Ɋm�F������Ő����B
�C�ӌ㌩���x�́A���C�Ȃ����ɐM���ł���㌩�l�����߂Ă������x�ł��B
�ړI: �����A�F�m�ǂȂǂŔ��f�\�͂��ቺ�����ۂɁA���Y�Ǘ�����x�����X���[�Y�ɍs��
�B�葱��: �_���������A�㌩�l�̖��������O�Ɍ��߂Ă���
�B�s�����m�̃T�|�[�g: �C�ӌ㌩�_�̍쐬���x���B�i���ۂ́A�㌩���x�T�|�[�g���̐搶�����Љ�邱�ƂɂȂ�܂��B�j
����s�����m�Ƃ��āAAI�R���T���^���g�Ƃ��āAAI���g���Ăł��邱�ƂJ�ɂ����������Ă��������܂��B
AI�ɊS�̂Ȃ�����A���S�҂̕��Ɏ�������Љ��Ƃ����Ă��̕����u�����I����Ȃ��Ƃ��ł���́B�v�Ƌ�����܂��B
�����J���Ȃ��NJ����鏕����: �ٗp�ێ���Y������Ȃǂ�ړI�Ƃ��A�ٗp�ی��������Ƃ�����̂ŁA�Љ�ی��J���m�̓Ɛ�Ɩ��ł��B
�o�ώY�ƏȂ�n�������c�́A�����J���ȈȊO�̏Ȓ����NJ�����⏕���E������: �Ɛ�I�ɐ\����s���s���m�Ƃ͑��݂����A�N�ł��\����s���\�ł����A�s�����m����\�I�ȑ��k��ł��B
�s�����m�́A���ƌv�揑�Ȃǂ̕K�v���ލ쐬�̃A�h�o�C�X��\����s�Ȃǂ̃T�|�[�g��ł��܂��B
�s�����m�Ɍ_�쐬���˗�����ہA�ȉ��̓_�ɒ��ӂ��K�v�ł��B
�������̂���Č��͑Ή��s��: ���Ƀg���u�����������Ă���_���A�@�I���X�N�̍����_�̍쐬�͍s�����m�ł͑Ή��ł��܂���B���̏ꍇ�ٌ͕�m�ɑ��k����K�v������܂��B
�_�Ɩ��������s�����m�������Ă���: ���ׂĂ̍s�����m���_�쐬����ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ����߁A�Ή��\�ȍs�����m��T�����Ƃ��d�v�ł��B
�s�����m�͖@�I���͂̂�����e�ؖ��X�ւ̍쐬�Ƒ��t���T�|�[�g�ł��܂��B
�ړI: �N�[�����O�I�t��Ԏӗ������ȂǁA��X�̃g���u����h�����߂ɗL��
�B�쐬�v���Z�X: �˗��҂̈ӎv�Ɋ�Â��A�K�ȏ��ނ��쐬
�B���t���@: ���e�ؖ��X�ւƂ��āA�����ɑ�����֑��t�B
���Ƃ̊J�n��^�c�ɕK�v�ȋ��F�̑��k�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȃ��̂��s�����m�֑������܂��B
���Ƌ���
�Y�Ɣp���������Ƌ���
�^���Ƌ���
���H�X�c�Ƌ���
�����c�Ƌ���
�Õ����c�Ƌ���
���s�Ɠo�^
�_�n�]�p���E�J�����B
���Ɍ��Ƌ��\���ł́A�p�ɂȖ@�����ɔ����\�����ނ̕ύX����p��Ɋւ��鑊�k�������A�ȉ��̏��ލ쐬�ɂ��Ă̑��k�������Ă��܂��B�E�������\�̍쐬�i���Ɠ��L�̉�v�����j�E
�����H�����D�֘A�̏���
���Ƌ����擾����ɂ́A���v����������ŁA�NJ��̋��s�����ɐ\�����܂��B
���̎��:
���ݍH����29�Ǝ킲�Ƃɋ����擾
��ʋ��Ɠ��苖�̂����ꂩ��I��
�\����:
�c�Ə���1�̓s���{���� �� �s���{���m���̋���
�B�c�Ə��������̓s���{���ɂ��� �� ���y��ʑ�b�̋���
�B���v��:
���o�c�Ɩ��̊Ǘ��\�́i�ӔC�Ґݒu�A�Љ�ی������Ȃǁj��
�c�Ə��ɐ�C�Z�p�҂�z�u
���������i�_���A�s���E�s�����ȍs�ׂ̂����ꂪ�Ȃ����Ɓj��
���Y�I��b�i�K�Ȏ��Y��L���Ă��邱�Ɓj
���y��ʑ�b���̏ꍇ�A�W���������Ԃ�90���ł��B���������ꍇ�́A���̊��Ԃ����Z����܂��B
���y��ʑ�b���̏ꍇ�A�\������͏o�̊e�l���ɂ����āA�\���҂�������ɂ�鉟�s�v�ƂȂ�܂����B�e�l������u��v���폜����Ă��܂��B�������A�s�����m�@�{�s�K����9���2���ɂ��L���E���s�v�Ƃ�����̂ł͂���܂���B
�����_��̌��ς�A���D�A�_������ȂǁA�����_��̒����ɌW����ԓI�ȍs�ׂ��s�����������w���܂��B���̉c�Ə��ɑ��Đ����_��Ɋւ���w���ē��s���ȂǁA���ƂɌW��c�ƂɎ����I�Ɋ֗^����ꍇ���c�Ə��ƂȂ�܂��B
�o�L��̖{�X�ł����Ă��A���ۂ͌��ƂɊւ���c�Ƃ��s��Ȃ��X�܂�A���ƂƖ��W�Ȏx�X�E�c�Ə��͊Y�����܂���B
�u�y���Ȍ��ݍH���v�݂̂𐿂������ꍇ�́A���Ƌ��͕s�v�ł��B��̓I�ɂ́A�ȉ��̏����ɊY������H���̂��Ȃ��Ő��������܂��B
�E���z�ꎮ�H��: �������1,500���~�i�ō��j���� �܂��� ���זʐ�150�u����
���z�ꎮ�H���ȊO�̌��ݍH���E �������500���~�i�ō��j�����B
��������̎Z��:
�_����ɕ��������ꍇ�͍��v�z�Ŕ��f
�����҂��ޗ�������ꍇ�͍ޗ�����܂߂Čv�Z
����ŁE�n������ł��܂߂����z�Ŕ��f
�B�����҂�����ޗ�������Z���A�ō�500���~�i���z�ꎮ�H���͐ō�1,500���~�j�ȏ�ɂȂ�ꍇ�͋����K�v�ł��B����̍H���͌y���ȍH���ł��o�^���K�v�i���T�C�N���@�Ɋ�Â���̍H���Ǝғo�^�j���H�����z��͐\�����̋��z��K�����m�F���������B
���Ƃ��c�މc�Ə��̏��ݒn��2�ȏ�̓s���{���ɑ�����ꍇ�́A���y��ʑ�b�̋����K�v�ł��B�c�Ə��̂Ȃ������Ō��ݍH�����{�H���邱�Ƃ͉\�ł��B
���Ƌ����擾������́A����I�Ȏ葱�����K�v�ł��B
�E���Z�̒�o: �����ƔN�x�I����A4�����ȓ��ɒ�o
�B�E���̍X�V: �L�����Ԃ�5�N�ԁA��������30���O�܂łɍX�V�B�E�\��
�ύX�͂̒�o: �����E���́E�����E���ݒn��ύX�����ꍇ�A30���ȓ��ɐ\���B�E
�Z�p�ҁE�ӔC�҂̕ύX��: �o�c�Ɩ��Ǘ��ӔC�҂��C�Z�p�҂���ւ����ꍇ�A14���ȓ��ɓ͂��o�B
������K�Ȏ葱�����K�v�Ȃ̂ŁA�v��I�ɑΉ����܂��傤�B
�u�ꎮ�H���v�̋����Ă��Ă��A�e���H���̋����Ă��Ȃ��ꍇ�́A500���~�ȏ�i�ō��j�̐��H����P�ƂŐ����������Ƃ͂ł��܂���B�Ⴆ�A���z�ꎮ�H���̋��������Ă��A�P�Ƃ�500���~�ȏ�̓����H���𐿂������ꍇ�͓����d��H���Ƃ̋����K�v�ł��B
���эH���Ƃ́A�傽�錚�ݍH����i�߂�ߒ��Ŕ�������⏕�I�ȍH���ł��B
�傽��H���̋��������OK �� �ʓr���͕s�v
�B�Ǝ҂�����{�H����ꍇ �� ���Z�p�҂̔z�u���K�v
�B�Ǝ҂��{�H���Ȃ��ꍇ �� �������Ǝ҂ɉ����{�H������K�v����B
�ȉ��̍�Ƃ͌��ݍH���ɊY�����܂���B�y���^���i�g���b�N���ł̉^���j
�����E����E���ؔ���
�B�����E�_���E�ȈՂȕ��i�����B
���i�̔��B
�{�ЁE�{�X�ŁA���߂�ꂽ���ԑтɌp���I�ɐE���ɏ]�����邱�Ƃ��w���܂��B
�c�Ə��ɏ���A���̐E������S������Z�p�҂̂��Ƃł��B
�����s�ł����A�ȉ��̏��������Η�O�I�ɉ\�ł��B
�E
�c�Ə��Ō_���H���ł��邱��
�B�E�H�����ꂪ�c�Ə��̋ߗׂł��邱�ƁB
�E
�c�Ə��Ə펞�A��������̐������邱�ƁB
�E�H�����z�����z�����i���z�ꎮ�H����7,000���~�����j�ł��邱�ƁB
�{�H���錚�ݍH���̎�ނɉ��������i���K�v�ł��B �ė��Z�p�҂ɂ́u�ė��Z�p�Ҏ��i�ҏv�̌�t�ƍu�K�̎�u���K�{�B
�������������A�������z��4,000���~�ȏ�i���z�ꎮ�H����8,000���~�ȏ�j�̍H���B����z�͊Y���N�x�̓K�p�z��K���������\�̂��̂Ƃ��m�F���������B
�����s�ł����A�_��H�����d������H���ň�̐�������ꍇ�͉\�B �܂��A��C�́u�ė��Z�p�ҕ⍲�v��z�u����A2�̍H���̌������\�i����ė��Z�p�ҁj�B